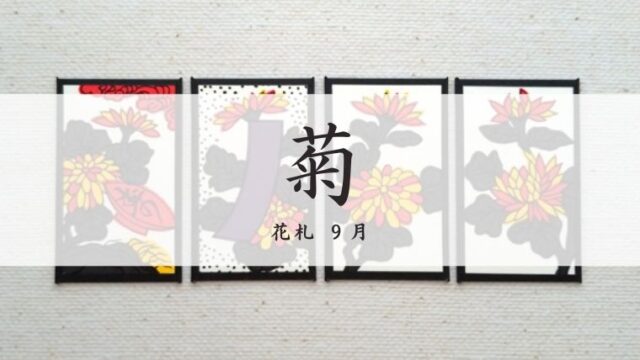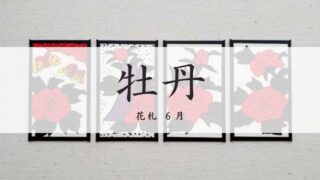花札10月の札は「鹿に紅葉」。
この札、ひと目で秋とわかるいいデザインですよね。
萩に猪や牡丹に蝶と並んでこちらも有名な花札になりますが、この鹿と紅葉の組み合わせ、どういった理由から選ばれたんでしょう。
たしかに紅葉は秋と関係があるにしろ、鹿はほかの動物でもよかったのでは?
いつものごとく今回も全力で調べたところ、驚いたことにある親子の悲しい物語が発端でした。
こんな情緒のある札に悲しみが隠れているなんて意外ですよね。
この由来を聞くと「鹿と紅葉」の札がまた違って見えるかもしれません。
それでは、鹿と紅葉が組み合わされたその由来となる物語を見ていくことにしましょう。
鹿と紅葉のきっかけとなった悲しい物語とは?
この花札の由来となる物語の舞台は、古くは奈良時代にさかのぼります。
ある日、興福寺というお寺の御堂で小僧さん達が習字の勉強をしていると、近くの奈良公園から一頭の鹿があらわれました。

その鹿が庭へ入り込み、小僧さん達が使っていた習字の紙を食べようとしたので、小僧の一人の三作(さんさく)が驚かせて追い払おうと手元にあった文鎮を鹿のあたりに投げつけました。
ところが驚かせるつもりで投げた文鎮が運悪く鹿の急所にあたってしまい、そのまま鹿は死んでしまいました。
当時、奈良公園にいる鹿は春日大社の神の使いと言われ、「鹿を殺した者は石詰の刑に処す」という掟があり、まだ子供の三作でも容赦なくその刑に処されることに。
三作が十三歳だったため、その歳にちなんだ一丈三寸(約4m)の井戸を掘り、三作と死んだ鹿を抱き合わせにして井戸の中に入れ、その上から石と瓦を詰めて三作は生き埋めにされてしまいました。
父親を早くに亡くし、母一人子一人で暮らしていた三作の母おみよは気が狂わんばかりに嘆き悲しみました。

せめてできることをと、朝(明けの七つ(午前4時)と夜(暮れの六つ(午後6時)に鐘をついて供養につとめました。
でも、自分が生きている間は供養として線香の一本も供えることができるけど、この世を去れば三作は鹿殺しの罪人として誰も花や線香を供えてくれる人はいないだろうと考え、おみよさんは花や線香の代わりに紅葉の木を植えたということです。

(終)
いかがだったでしょうか。
十三歳のわが子がわざとではないにしろ鹿を殺め罪人とされ、しかも生き埋めという残酷なやり方で処刑されてしまった。
そんな母親の気持ちを思うと心が痛みますよね・・・。
この切ないお話がのちに「鹿と紅葉」の札の誕生のきっかけとなったんです。
このお話が「鹿と紅葉」の札になるまで
江戸時代の人々はこのお話に心を打たれた
この切ない話は、江戸時代に近松門左衛門が浄瑠璃として発表しました。
その名は「十三鐘(じゅうさんがね)」。
おみよさんが三作の供養のために、明け方七つと暮れの六つに両方の時の数をあわせた十三回鐘をついたことから、この鐘は「十三鐘」と呼ばれるようになり、浄瑠璃にもそのまま名付けられました。
残酷で切ない話と子を思う母の愛に人々が心を打たれ、この浄瑠璃は大ヒットします。
浄瑠璃から花札に鹿と紅葉が採用された
花札のデザインが考えられたのは、まさにこの浄瑠璃が大ヒットした江戸時代。
花札の10月(=旧暦の10月。今の10月下旬から12月上旬ごろ)はちょうど紅葉が色づく頃だったので、流行りの浄瑠璃に出てくる「鹿と紅葉」をこの札のデザインに採用したというわけなんです。
「秋といえば十三鐘」ということで、即決で花札10月のデザインに決まったんでしょうね。
「十三鐘」の舞台は今も実在する
ちなみに「十三鐘」の舞台となったお寺は、今も実在するお寺です。
奈良県の興福寺というお寺で、ここには三作が習字を習っていた大御堂や処刑された場所、また母のおみよさんが供養のためについていた鐘も残っています。
「十三鐘」は、奈艮で明けの七ツと六ツの間に撞いた鐘この鐘が撞かれる時刻に、三作という少年が鹿殺しの罪で石子詰の刑に
— 青によし🐯 (@nara_mahoroba) November 25, 2019
刑の執行を告げるその鐘を音を聞く母親の嘆きを歌ったものが、浄瑠璃「十三鐘」
鹿殺しの罪で、鹿と一緒に生き埋めにされた息子の霊の供養に、母が紅葉の木を植えました pic.twitter.com/kOxNbgkoV3
また三作の供養塔もあり、こちらは三作の寿命があまりにも短かったため「生まれ変わった時は長生きできますように」との思いを込めて、亀の上に供養塔が建てられています。
興福寺、菩提院にある三作石子詰供養塔は、三作が生まれ変わったら、長生きできるように願って、亀の背中に五輪塔が建てられています。 pic.twitter.com/Fcp07NMO
— easysailing (@easysailing3239) June 1, 2012
興福寺は奈良公園や春日大社の近くにあるので、観光の際に少し足をのばして三作を思いながら訪れるのもいいかもしれませんね。
「しかと」はこの花札が由来の言葉
無視したり、仲間はずれにすることを「しかとする」と言いますが、この語源は鹿と紅葉の花札が由来と言われています。

鹿がこちらを見ずにそっぽを向いていることと、また鹿が10月の札であることから「しか10(と)=しかと」という言葉が生まれたと言われています。
まとめ
- 鹿と紅葉の花札のデザインは残酷で切ない「十三鐘」というお話が発端
- 江戸時代に浄瑠璃で十三鐘が大ヒット!それが花札10月のデザインのきっかけとなった
- 十三鐘のお話の舞台は今も実在している
しかとは花札の鹿がそっぽを向いていることが語源だったけど、私にはこの札は鹿が紅葉の下に眠っている三作を申し訳なさそうに見ているように見えるんですよね。
「紙食べたことでなんか大事になってごめんね・・・」みたいな。
今までは秋らしいきれいな札だなぐらいしか思ってなかったけど、これからはちょっと見るたびに切なくなりそうです。